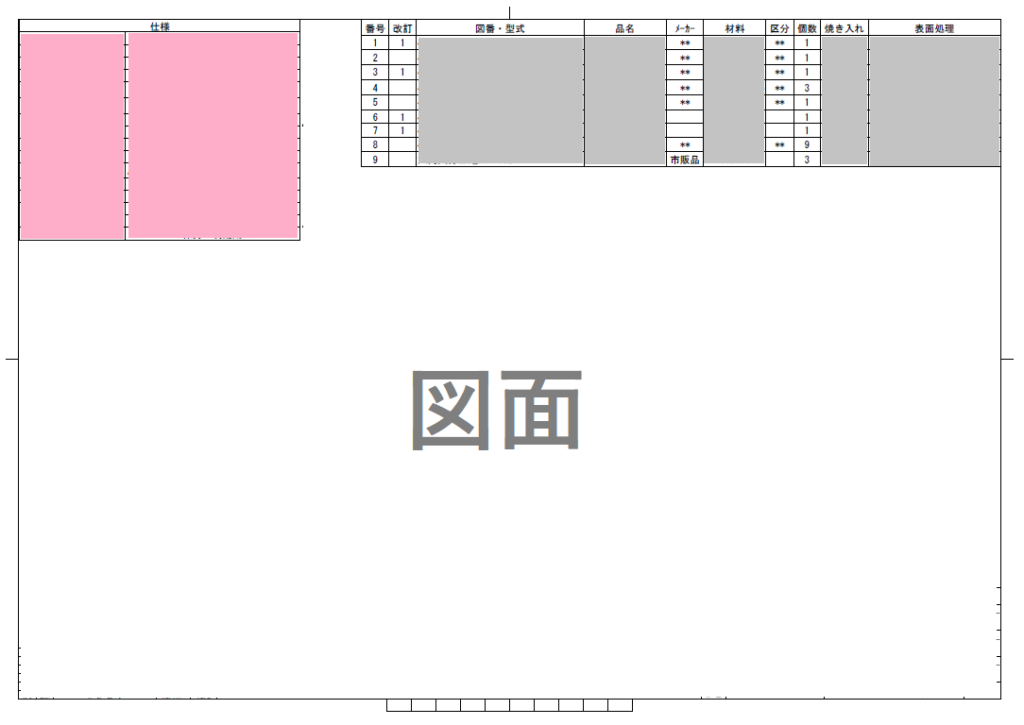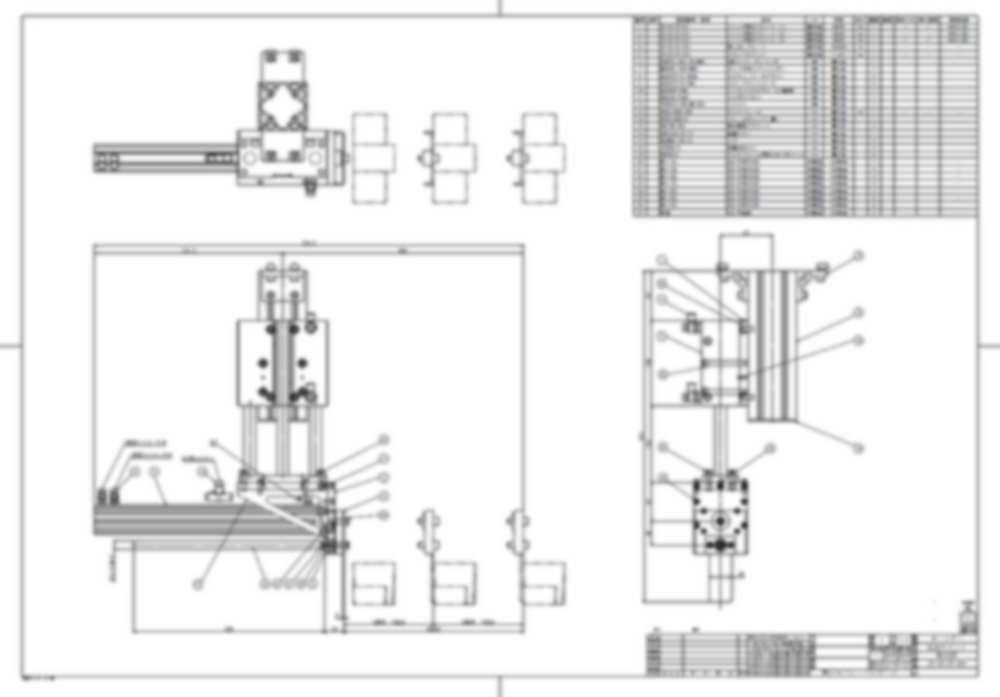今日は 「機械設計における組立図の書き方」 についてをメモします。
3DCADの普及により 従来より組立図を書く機会も少なくなってきているように見えますが、組立図というのは、実際に組み立てるときだけに必要な図面ではない ので、機械設計者はこの組立図をいつでも適切に書けるようになっておくと良いと思います。
組立図とは
組立図というのは 複数部品が組み合わさった完成品が図面になっている わけですが、 ほんの数点の部品が組み上がる製品ならすぐ書けるものの 部品点数が増えれば増えるほど組立図は難しくなってきます。
組立図をどう書いたら良いか解らない(特に初心者)方にとって、組立図を作るのは苦痛だと思うんですが、そもそも 組立図に書いていく内容は各企業の内部だけで作り上げられる外に出ないノウハウの塊 です。
その為、初めから組立図を書ける設計者はおらず、長い年月を掛け、色々な経験をして最適な組立図が書けるようになると思います。 私の場合、3DCADによる作図をしているので、各面一瞬で出せますし、断面も自由自在。風船も打ち込む事がなく、2次元CADの時よりも負荷が減ってきていてそれほど苦ではないです。
どちらかというと好きな作業です。
その組立図は、CADでも手書きでも 求められる要素は同じ なので、 組立図ってどうあるべきなのか を軸にしながら組立図の書き方を以下メモしいきます。
組立図の定義
組立図の定義って皆さん知っていますでしょうか? ものづくりWEBの「組立図の書き方 - 機械設計エンジニアの基礎知識」にはこんなことが書いてあります。
引用(ものづくりWEBより)
組立図は製品全体を表せるように 正面図、平面図、側面図 の3方向のビューで表し必要に応じてその他の投影図や断面図を追加します。
組立図には製品全体の最外形(製品の大きさ)の寸法を記入します。
その他で、辞書関連で行くとこんなことが書いてありました。
引用(大車林さんより)
複数の部品を組み立てて、機能上、または取り扱い上のまとまり状態を表現した図面。アッシー図ともいい、部品図と区別して呼ばれている。
組立図だけで対象製品や対象部位の全体像は把握できるが、個々の部品・部位の詳細についての情報量が不足しがち。それを補完するために部品図や詳細図を併用して使われることが多い。単純な組立て図の場合は、個々の構成部品に形状寸法や仕様を併記して、部品図や詳細図を兼ねる手法も使われている。
以上のように組立図の説明が書かれています。 要するに組立図の書き方は設計者次第 ということが解りますよね。
組立図に必要な項目は大きく分けて「3つ」ある
さて、ここからは私の考えを書いていきます。
組立図を書くに当たって、ベースとなる考えは 「誰が見ても、何がどうなっているか解るもの」 ですが、そのために組立図へ記載する必要のあるもの大きく分けて3つあります。
- 設計者・設備管理者向けの 能力値(テキスト)を記載 すること
- 組立・調整者向けに、 機械を組み立てるための情報(寸法など)を記載 すること
- 発注に必要な 部品表や風船を記載 すること
この3つです。 複数のユニットによって構成される機械になると、上記を 全体図、部分組立図 などの階層ごと組立図を作っていきます。
- 全体図(ユニットA/B/Cが組み合わさったもの)
- ユニットA 組立図
- ユニットB 組立図
- ユニットC 組立図
こんなイメージです。
① 設計者・設備管理者向けの能力値(テキストや表)
1つ目の「設計者・設備管理者」向けの能力値(許容値)とは、この機械は どの速度でどう動くとか、他の設備との関連性だとか、可搬重量は最大ここまでとか そんな能力を数値で記載する事 です。
上の図でいうと左上の 薄赤部(場所は問わない)に表を作り 左に項目、右に値 の表を作って貼るなどをします。(ちなみに右上は部品表)
冒頭で、実際に組み立てるときだけに必要な図面ではない と書きましたが、まさにこの部分 で、ここで書いた組立図を使ってDRをしたり、CADモデルを開けない部署へ回ったり、設計完了前にも組立図が必要になってきます。 組立図をDRに持ち込むメリットは 俯瞰的にその機械を見ることができ、モデルでは確認に手間のかかる寸法を全体を見渡すことができる こと です。
組立図が不要という人の多くに 今は3Dモデルを見ながら組み立てられるから不要 という意見もありますが、それは各シチュエーション別で必要性が変わってくるので、DRなど組立以外のポイントでも使われることを考えると 半分正解で半分間違っている と個人的には思っています。
② 組立・調整者向けに、機械を組み立てるための情報(寸法)を入れる
2つ目の「組立・調整者」向けには、その機械を組み立てるための情報を入れていきます。 例えば、
- 部品同士をどう当て付けて固定する とかのコメントを入れたり
- 特定の調整ネジはこの寸法で取り付ける必要がある とかコメントを入れたり
- 特定のねじに対して締め付けトルクは何N・mです とかコメントを入れたり
- 搬送レベルの高さはこの高さです とかコメントを入れたり
こんな内容です。 上記のような言葉で表すしかない方法もありますが、基本的には「寸法」によって表現する事が多い です。 組立図寸法の入れ方については別途 組立図寸法の入れ方 というページがあるのでそちらをご確認ください。
寸法入れや要所要所のコメントは 関わるそれぞれの 「担当者としての目線」 で組立図を書いていけばいいと思います。 出図以降関わる担当者はどんな情報を組立図から読み取りたいのか。 を考えながら記入していくということです。
③ 部品表を載せそれに連動する風船を各部品に上げる
組立図には 漏れがない部品表と上げ忘れのない風船が必要 です。
画像はイメージ把握用のオリジナル画像用で作成したものですので少し雑です・・・。
どの部品がどこにつくのか、締結に座金が必要か、材質はSUSなのか など、細かい情報に風船をたどって確認できるようにします。 よろしければ 図面内に必要な部品表の参考 をご確認ください。
このように、 組立図というのはその対象となるユニットの 外形・寸法・仕様・構成が解るようにされた図面 を指します。
組立図作図でとても重要な事
組立図を書く上でとても大切な事だと思うのは 誰が見ても、何がどうなっているか解るものを書くという意識 だと思っています。
その図面は、これから多くの人に利用されるんです。図面って、将来の可能性を左右する大切な物なんですよ。 たかが1分のレイアウトを考える時間にどれだけ未来の効率化が出来るのか。 誰でも解るくらいシンプルで解りやすいものだとしたら、それに関わる人達の図面を眺める時間が個々では短い時間かもしれませんが、まとめるとかなりの効果になるんです。 ただ単純にお絵かきだと捉えているとだめ なんです。
図面は組立図・部品図共に誰が見るか特定できません。 特に組立図の書き方はセンスが分かれるところ。
その組立図を見るのは一人じゃなくて最終的にどこの階層の人まで見るか解りませんから、経験を色々と積んでいく中で自分なりの表現方法・表現の仕方を増やすしかない と思っています。 図面のレイアウトにしても、寸法の入れるべき所や注記を書く必要があるところを見せようと思ったら、おのずと正面・平面・右側面・部分詳細図・断面図などが決まってくる と思います。
そして きれいな図面は仕事もきれいに収める ことができるので、私たち設計者は組立図に対して拘りを持つことも大切だと考えています。
これが組立図の基本です。 以上です。
-

-
図面の書き方
図面の書き方(全般) ここでは、 各種の図面の書き方 をまとめています。 図面を書くにあたって 参考になるような内容があれば幸いです。 JISで推奨されている図面尺度と実用的な図面尺度 図枠に関する情 ...
続きを見る